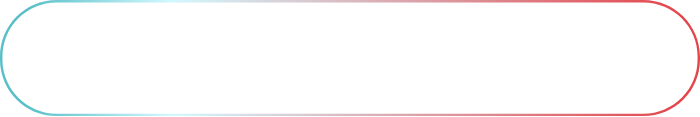南部美人の酒づくり 「もろみ」編
仕込みは「初添」「仲添」「溜添」の3段階で
さて、麹と酒母が出来上がるといよいよ仕込みになります。
普通日本酒の仕込みは麹米と掛け米(洗って蒸した米)と水をタンクに入れて仕込みますが、一度に全部入れるのではなく、三段(三回に分けて)で仕込みます。
一回目を「初添」、一日間をおいて(これを踊りという)二回目が「仲添」、三回目が「留添」と言い、だんだんと米の量を多くして仕込みます。

総米700kgの仕込みですと、「添」が35kgの麹米と85kgの掛け米と147Lの仕込み水、「仲」が45kgの麹米と195kgの掛け米と313Lの仕込み水、「留が48kgの麹米と242kgの掛け米と242Lの仕込み水で仕込みます。
仕込み温度は「初添」が約13度、「仲添」が約8度、「留添」が約6度と、だんだんと温度を下げて仕込みます。「留添」を仕込んでから約7日から10日かけて10度から13度の最高温度に到達させます。この事からもわかるように、日本酒は低温で仕込み、低温で発酵させますので寒い冬にしか仕込むことができません。
南部美人では、「初添」のところで特徴ある仕込みをします。通常ならば「初添」は大きなタンクに直接仕込むのですが、南部美人では「枝桶」と言われる小さな桶を使い、そちらに仕込みます。
なぜそんなことをするかというと、岩手県北の冬はとても寒く、仕込み蔵も大変温度が低いです。その低い室温で大きなタンクに少量の初添を仕込むと、品温が低下してしまい、酵母の初期発育にダメージを与えてしまうので、13度くらいで仕込みたい初添を20度くらいまで温度をあげなければいけません。
そういう事をしないために、小さなタンクの枝桶を使い、しっかりと保温できるようにして13度で仕込みます。
その後、大きなタンクに返して仲添、留添とするので、大きなタンクに返す手間が増えるのですが、初添の温度を正確にしたいために、手間を惜しまずにこの古き伝統的な方法を今でも使っています。
最高温度は大吟醸などでは約10度ですが、純米酒や本醸造は12度から13度と少し高めにし、米の味を最大限に引き出すようにしています。大吟醸は約10度という酵母にとって生きるか死ぬかの限界で発酵させることにより、あのすばらしい吟醸香が出てきます。
もろみの泡は5日目から7日目位が最高に出て、その後自然ともろみの仲に消えていき、消える寸前に玉泡となり、12日目位になるとすっかりと泡がなくなってしまいます。この泡のなくなった状態を「地」といいます。その間人間は朝一回だけ櫂入れ(もろみをかき混ぜること)をするだけです。
泡が出てくるとタンクからこぼれてしまうときがあるので「泡がさ」をタンクの上に置いてこぼれないようにします。それでも泡が高く上がってくるときは泡消し機を使い泡を押さえます。
最近ではこの泡のない酵母もたくさん出てきましたが、南部美人では蔵人が若いため、経験が少ないです。よって、もろみの状態を分析だけで判断するのではなく、泡の状態でも判断できるように泡のある酵母を使っています。しかし泡がさをかけたりする手間が必要なので、泡のある酵母はだんだんと使われなくなってきています。

「留添」を仕込んでから15日目くらいになると、発酵が進んできますので少しずつ温度を下げていきます。温度を下げる手段はタンクに巻いたマットに冷水が通りもろみの温度を下げます。約7日かけて温度を10度から6度まで下げて、もろみの発酵を押さえます。
発酵期間の約30日の間、大吟醸は毎日もろみを少量とり、日本酒度、酸度、アミノ酸度、アルコールなどの分析をします。純米酒や本醸造は二日に一度もろみをとり分析します。
「南部美人ではもろみの分析は自動分析機を使い、正確な数値を把握し、時間の短縮もしています。それにより、もろみ管理の正確性を大切にしています。さらに、日本酒度やアルコール度数のほかに、現代の日本酒造りで大切にされているグルコースの管理も出来る分析器を用意して、グルコース管理も徹底しています。」

SD-700迅速アルコール測定キット
日本酒度・アルコール自動測定します

AT-710総酸・アミノ酸計パック
CHAL-700多検体チェンジャー(11検体)
総酸・アミノ酸自動測定します

分光光度計 グルコース測定
こうして、約30日かけてお酒は出来上がります。低温で長期発酵させることにより、米の味と上品な香りを引き出したいと考えています。こうして発酵が終了したもろみをいよいよしぼります。